有吉佐和子さんの『非色』を読みました。
この物語を読み、何を思えばいいのだろう。
想像以上の重いショックに数日頭がぼーっとしてしまいました。

どんなおはなし?
色に非ず―。終戦直後黒人兵と結婚し、幼い子を連れニューヨークに渡った笑子だが、待っていたのは貧民街ハアレムでの半地下生活だった。人種差別と偏見にあいながらも、「差別とは何か?」を問い続け、逞しく生き方を模索する。一九六四年、著者がニューヨーク留学後にアメリカの人種問題を内面から描いた渾身の傑作長編。(本書裏表紙より)
読んだ感想
人種差別なんて代表的な社会問題として認知していたはずなのに、結局私はなにひとつ知らなかったことを思い知らされました。
この物語は、「ニグロ」として差別される人間、その伴侶である日本人から見た人種差別を描いています。
終戦後の日本には「戦争花嫁」といって日本にいる米兵と結婚する日本人女性が約4万人いたといいます。しかし当時の日本では、戦争花嫁は娼婦と揶揄されるなど、偏見の目で見られることが多かったようです。
主人公の笑子もその戦争花嫁とされる一人ですが、この笑子という人間が本当に強い。黒人との結婚に世間の目は冷たく、黒い肌を理由にその人間性までもを否定するような人ばかりでした。同じく黒い肌をもつ娘のために日本を離れたものの、アメリカにはもっと複雑な人種差別が蔓延っており、笑子の人生はその後も波乱に満ちたものになります。
基本的に反骨精神が強く、少々手荒な生き方をする笑子ですが、自分が受ける差別に対しては躍起になって反発するというよりも、その差別構造や差別行為の根底にある人間の心理を突き詰めようとする冷静な視点を持っています。
黒人との結婚に対し、身分が不釣り合いだと説く母親に違和感を抱いた笑子が印象的でした。このときの疑問が後にアメリカで嫌というほど体感する差別の構造を紐解くヒントになっているように思えます。
なにか人間としての尊厳が軽んじられたり、脅かされるとき、普段は意識もしないような大きなもので自分を括り、身を守ろうとする心理はなんなのでしょう。種族や身分を盾にして、個人としての自分を守ろうとする防衛反応なのでしょうか。
笑子は、”人種のるつぼ”であるニューヨークの地で単なる白人対黒人だけではなく、ユダヤ人、イタリア人、プエルトリコ人、アフリカ系黒人、アメリカ系黒人など、実に複雑な人種差別を目の当たりにします。不当な暮らしを強いられ、普段は何事にも無気力な「ニグロ」の夫さえ、さらに下位階級に位置づけられるプエルトリコ人の存在には、生き生きとした口調で蔑みます。
笑子は何度も考えます。「差別は肌の色に非(あら)ず」ということ。そして、人間が生きていくうえで心の支えとするものは、自分は誰かよりも優れているという確信をもつことなのだという考えに行きつきます。
優越感こそがバイタリティーであり、幸せの尺度でもある、そのように読みかえることができますが、この極端とも思える思想は現代の人間にも当てはまるのではないかと思います。私たちは無意識のうちに他人を分かりやすいものにカテゴライズし、それが自分よりも上か下どちらに属するものか、社会的序列を瞬時にジャッジする癖があります。劣等感に苦しみ、優越感に安心を抱く。その濃淡の度合いはあれど、人間誰しも生きている限りどこまでも他人との比較がつきまといます。ましてや、健康で文化的な最低限度の生活が脅かされる環境においては、この醜いとも思える優越感が唯一の生きるエネルギーとなるのかもしれません。
そして物語の終盤、ワシントンの桜並木の場面に心が打たれました。
猛々と咲き誇るワシントンの桜。笑子の目には儚げに花びら舞う日本の桜とはもはや別物に映ります。
そこで、笑子は気づくのです。
いつまでも外側から見ていては何も分からないし、変わらない。桜が風土によって性質を変えたように、自分も内側から染まり、生き方を変えなければならないのだと。夫や子供たちと同じように、この地で「二グロ」として生きていかなければ。
そう決心する笑子にはもう迷いはなく、これからも続くであろう茨の道に確かな希望を持ちながら歩み出す姿で物語が終わります。
社会問題はひとりの経験に落とし込んで初めてその実態を知ることができるように思います。教科書や新聞の見出しからは想像に及ばない、ひとりの人間の人生がここに描かれていました。
50年以上前に書かれた作品とは思えないほど、今にも通ずるものの考え方で綴られており、スピーディーな展開ながらも、そこにちゃんと気持ちを落とし込んで読みすすめることができました。
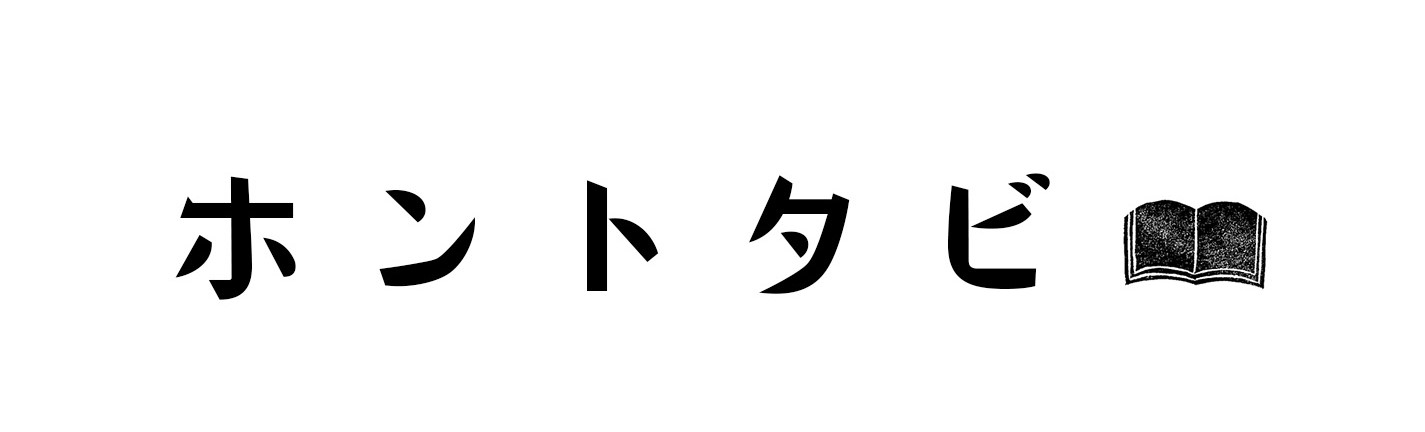



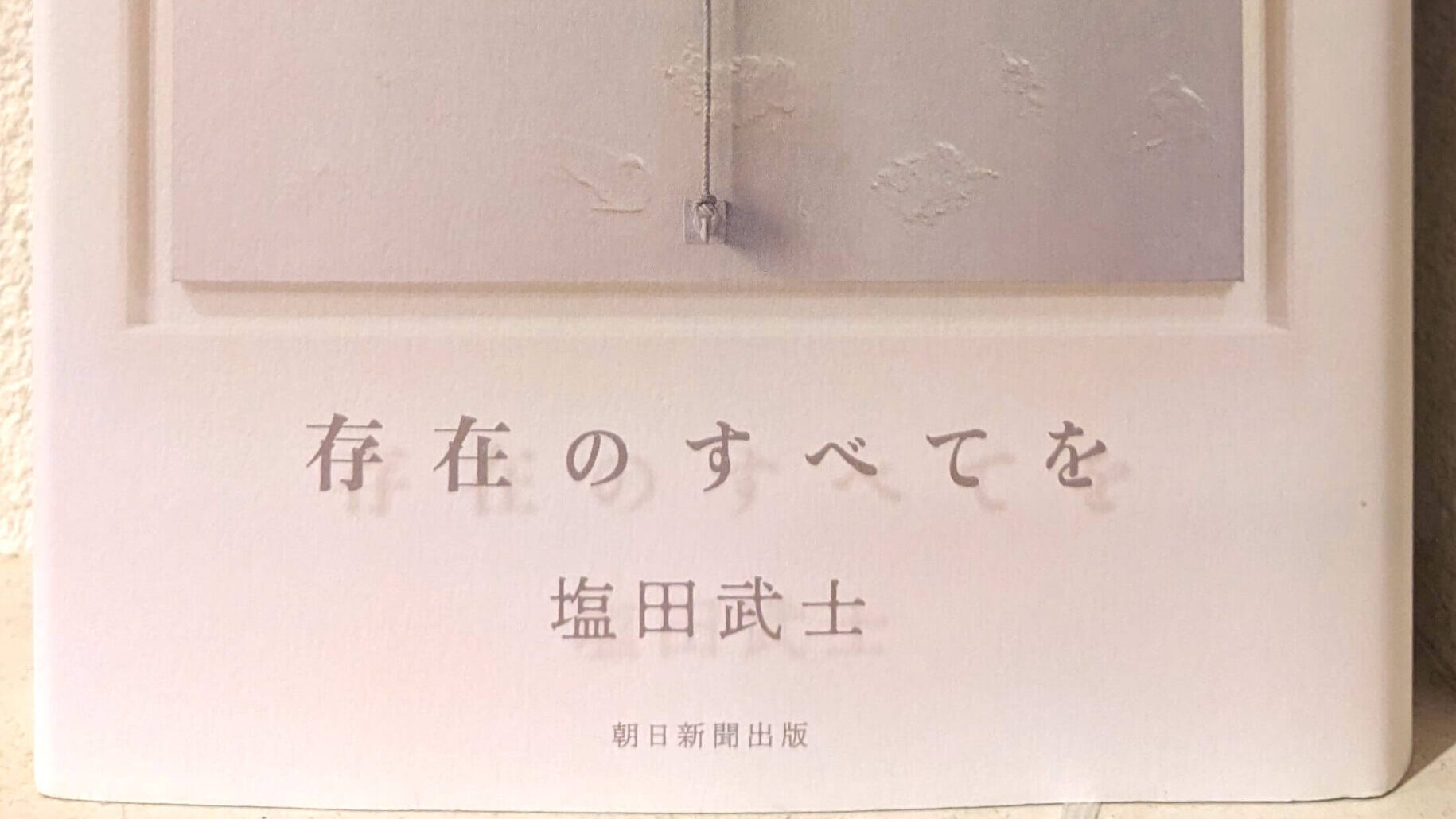
コメント