湊かなえさんの『母性』を読みました。
湊かなえさんの作品は久しぶりに読みましたが、やはりこの独白を主軸にストーリーが紡がれていくスタイルは一気に不気味な世界観に引き込まれますね。

愛という独りよがりで形のないもの。さらに、母から娘への“母性”という、これまた厄介な愛情。
視点が変われば、こんなにも愛情は歪んでしまうものかと少し恐怖を感じました。
どんなおはなし?
女子高生が自宅の中庭で倒れているのが発見された。
母親は言葉を詰まらせる。「愛能う限り、大切に育ててきた娘がこんなことになるなんて」。 世間は騒ぐ。これは事故か、自殺か。
……遡ること十一年前の台風の日、彼女たちを包んだ幸福は、突如奪い去られていた。
母の手記と娘の回想が交錯し、浮かび上がる真相。これは事故か、それとも――。
圧倒的に新しい、「母と娘」を巡る物語(ミステリー)。(「BOOK」データベースより)
読んだ感想
自分が子を持ち、子という立場から親という立場に移行するとき、自然と愛情の向け先も変わっていくもの。しかし、なかにはこの当たり前とも思えるステップに躓く人間もいるのだと気づかされました。だから世の中には悲惨な事件が起きるのかもしれません。
ルミ子は娘が喜ぶことよりも、自分が母に褒められたい、母を喜ばせたいという気持ちが勝り、自分の母を少しでも傷つけるような、自分の娘の言動には腹だたしさを感じるほど。自分は常に母の好む言葉、仕草、行動を選んできたのに、なぜ娘はそれができないのか。ルミ子の母への異常な愛は恐怖ものです。
しかし、ルミ子は娘の命と引きかえに最愛の母を亡くしてしまいます。
悲痛な母との別れと同時に始まった意地悪な義父母との同居はルミ子の心を壊し、その矛先は愛する娘へと向かいます。愛したいのに。愛されたいのに。母娘の互いの愛情がますます捻じれていく様子は読んでいてとても息苦しい。
ルミ子含め、この小説にまともな人間は登場しません。みんな何かが過剰で何かが不足していて、その度合いがあまりにもアンバランスな人達ばかり。自分の欲求や愛情をうまく言葉と態度に表せず、常に衝突。ただ愛されたいと願う娘の気持ちが一番まっすぐで、その健気さに胸が詰まります。
物語の終盤、娘が母性について語る場面があります。簡潔ながらも、私のなかでとても腑に落ちる一節でした。
受け取ったものではなく、求めたものを捧げる。
誰もが誰かの子を経験したからこそ、気づける愛のかたちがあるのだとハッとさせられました。
そして、この小説には湊かなえ作品らしい仕掛けが施されています。読んでいる途中に「ん?」と引っかかる数箇所がポイント。私は読後に頭を整理しているとき、あっなるほど!と気が付きました。
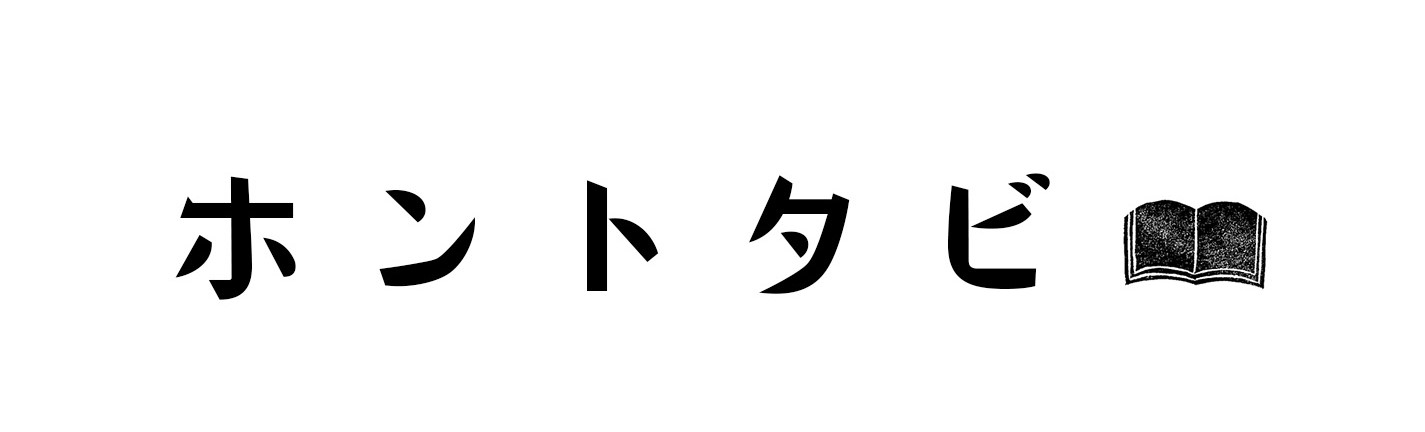


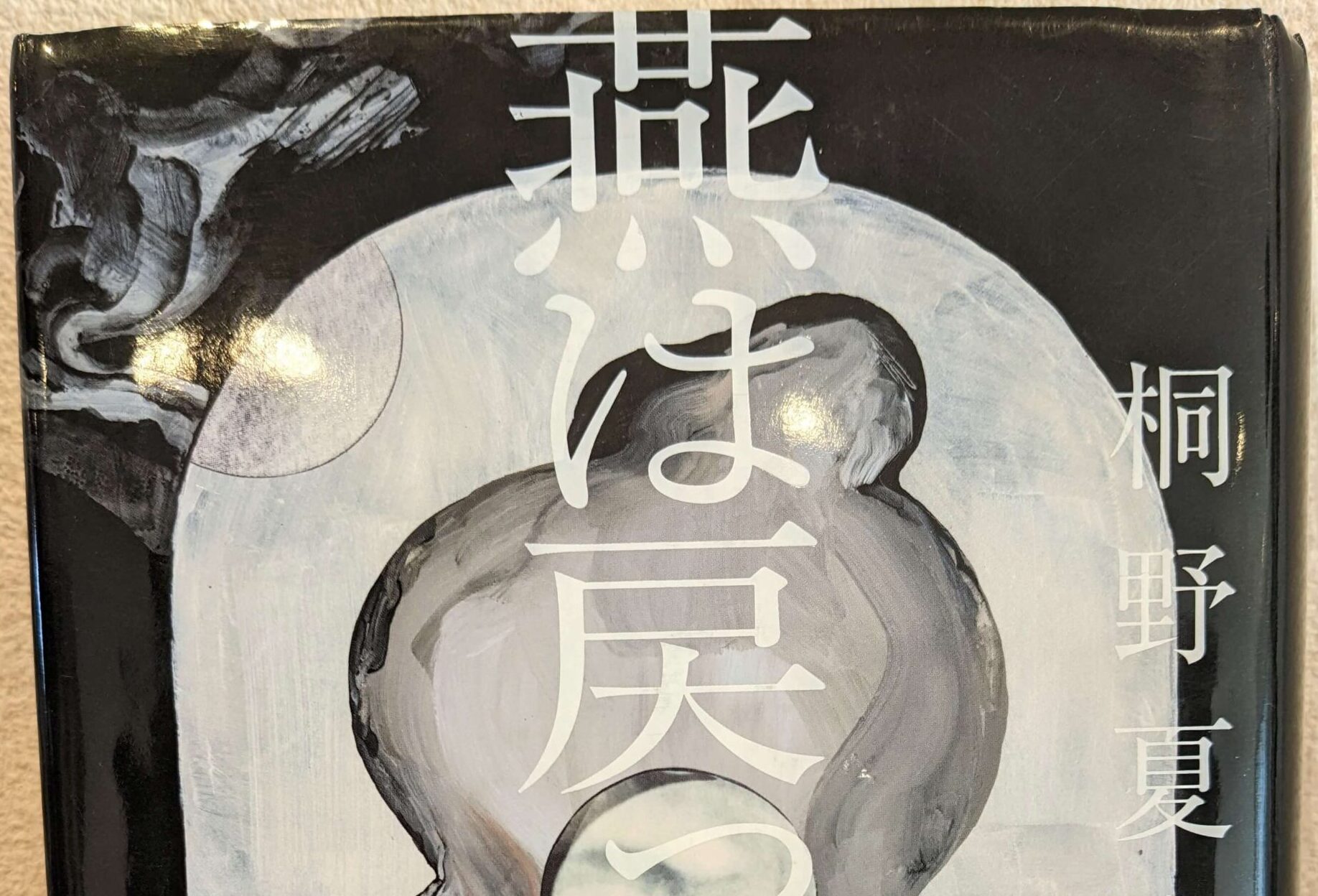
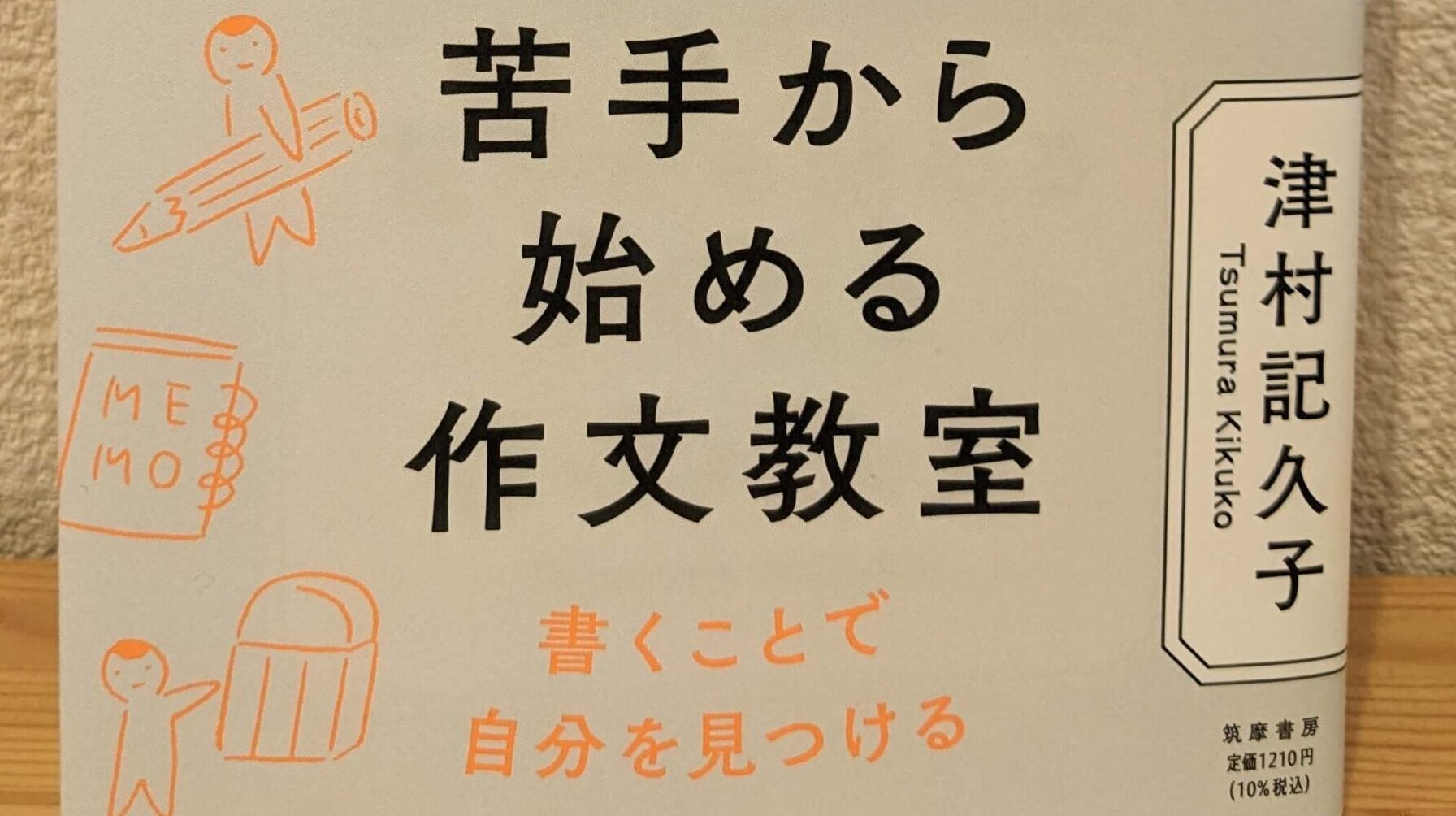
コメント